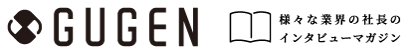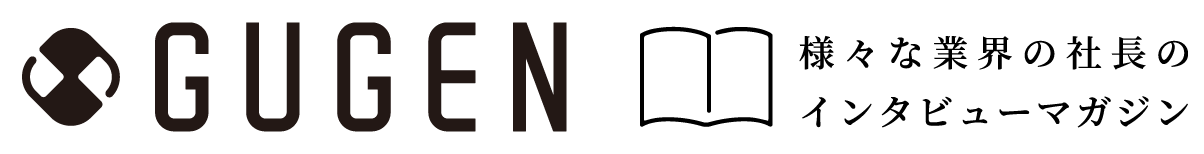「また長野の経済団体で動きがあったぞ!」──そんな声が地元ビジネスパーソンの間で飛び交っています。そう、今回は“長野県経営者協会”という県内有数の経済団体で、大きな人事のニュースが発表されたのです。
2025年5月、現会長の碓井稔氏が退任し、後任として八十二銀行の頭取である松下正樹氏が新会長に就任予定と報じられました。
「え? 八十二銀行ってまた会長やるの?」「セイコーエプソンからのバトンってどういうこと?」――そう感じた方、少なくないはずです。
経済団体の会長人事なんて、普段あまり注目されないかもしれません。でも、だからこそ!実はこの人事こそが、今後の県内企業の成長や支援体制に影響してくる重要な“動き”なのです。
そこで今回は、長野県経営者協会の会長交代をめぐる背景から、新体制による展望まで、しっかりと解説していきます!

長野県経営者協会の新会長に松下正樹氏が内定
──地域経済の“顔”が変わる、その意味とは?
長野県経営者協会が発表した新会長の内定――このニュースは、地元経済にとって見逃せない大きなトピックです。次期会長には、現在八十二銀行の頭取を務める松下正樹氏が就任予定とされ、2025年5月の総会で正式決定される見込みです。
「えっ、また銀行出身者なの?」と思ったあなた、鋭い!実は、八十二銀行出身者の会長就任は、山浦愛幸氏(2009~2021年)以来のこと。つまり、4年ぶりの“地元金融”からのリーダー復活というわけです。
しかもこのタイミング、実に絶妙。会長職を務めてきたセイコーエプソン相談役・碓井稔氏が任期満了を迎える中でのバトンタッチ。単なる人事交代ではなく、「地域金融」「製造業」という異なる視点を持つトップからの交代劇は、県内の経済戦略にも大きく影響を与えることが予想されます。
次節では、そんな松下氏の人物像や経歴、これまでの実績を深掘りしながら、「なぜ彼が選ばれたのか?」を探っていきましょう!
2025年5月に正式就任、4年ぶりの会長交代
──経営者協会のトップが変わることの重み
今回の会長交代は、実に4年ぶり。前任の碓井稔氏が2021年に就任してから、地域経済に寄り添う形で様々な支援策や産学官連携を推進してきました。そんな碓井氏が、任期満了により円満退任を迎えるのは、地元経済界にとって一つの区切りと言えるでしょう。
新たに会長に内定した松下正樹氏は、現職の八十二銀行頭取であり、同協会の副会長も兼任してきた人物。金融畑を歩んできたそのキャリアは、リスクマネジメントや地域投資の視点に長けており、安定感と現場感の両方を備えたリーダーです。
「会長ってそんなに影響力あるの?」と感じた方、ちょっと待ってください。長野県経営者協会は、地元の主要企業が結集する“経済界の司令塔”のような存在です。会長の交代は、単なる人事ではなく、経済政策の舵取りが変わることを意味します。
特に今回は、セイコーエプソンのような製造業界の代表から、地方銀行という“金融の軸”へバトンが渡るため、県内の資金循環や投資先戦略にも影響を及ぼす可能性が高いのです。
次は、松下氏がどのようなキャリアを持ち、どのような“武器”を備えてこの会長職に臨もうとしているのか、具体的に掘り下げていきましょう。
松下正樹氏の経歴と八十二銀行での実績
──地域金融の最前線で培った“現場主義”が強み!
なぜ松下正樹氏が長野県経営者協会の新会長に選ばれたのか?その答えは、彼の歩んできたキャリアと、地域金融の中核でのリーダー経験にあります。
松下氏は、八十二銀行に長年在籍し、現在は同行の頭取を務めています。長野県内で圧倒的な存在感を持つ地方銀行を率いながら、近年では「地域密着型の融資」「地方創生プロジェクトへの資金提供」「中小企業支援のスキーム構築」など、経済活性化に向けたさまざまな取組みを主導してきました。
また、長野県銀行協会の会長も務めており、金融セクターだけでなく、産業界や自治体との橋渡し役としての信頼も厚い存在です。
「銀行の人って、ちょっと堅そう…」と思う方もいるかもしれません。しかし松下氏は、現場での対話を重視し、経営者たちとフラットに意見交換する“顔が見えるトップ”として知られています。
その実績の一つとして評価されているのが、八十二銀行が手がける「地方創生連携ファンド」の創設。地元企業やスタートアップへの成長資金供給を通じて、地域に“稼ぐ力”を取り戻すことに貢献してきました。
こうした「金融の視点」と「地元経済の現場感」を併せ持つ人物こそが、次の長野県経営者協会を率いるにふさわしいと判断されたわけです。
次は、今回の会長交代が注目される理由と、経営者協会が担っている重要な役割について掘り下げていきます!
なぜ今、経営者協会の会長交代が注目されるのか?
──単なる人事ではなく、地域経済の“未来図”に直結する一手
今回の会長交代が注目されているのは、単なる“トップのすげ替え”ではないからです。経営者協会のリーダーは、県内企業や自治体、教育機関と連携し、地元経済の方向性を形作る非常に重要なポジション。
とくに、今は中小企業の後継者不足や、地方の人口減少、デジタル化の波など、地域経済が大きく揺らぐタイミング。だからこそ「誰がこの組織を率いるのか?」が、非常に重要な意味を持つのです。
また、八十二銀行という金融の中枢から選ばれた松下氏が会長に就任することで、県内の資金循環や投資の方向性も変化が予想されます。つまり、地域経済の地図が“書き換わる”可能性があるということ。
次からは、長野県経営者協会が果たしている具体的な役割、そして前任の碓井稔氏が残してきた功績について解説していきます!
長野県経営者協会の役割と地域経済への影響
──“経済界のハブ”として果たす調整力と発信力
長野県経営者協会は、県内の主要企業を中心に構成される経済団体で、その活動は単なる業界交流にとどまりません。むしろ、県政や市町村との政策協議、労働行政、教育連携、さらには海外展開まで、多岐にわたる調整と提言を担っています。
「そんなに影響力あるの?」と思われる方もいるかもしれませんが、たとえば労働環境の改善や賃上げ交渉、インターンシップ制度の導入など、企業単体では動かしづらいテーマを、経営者協会が“まとめ役”として主導しているのです。
また、経営者協会が地元大学や専門学校と連携し、「産学連携プロジェクト」を進めることで、若年層の地元定着や人材育成のインフラとしての機能も担っています。
経済団体の中でも、これだけ多角的な役割を担っている組織は少なく、長野県内ではまさに“経済界のハブ”的存在。その会長が変わるということは、政策提言のスタイルや企業支援の方向性にも変化が起きるということなのです。
次のセクションでは、退任する碓井稔氏がどのような業績を残し、松下氏にどんなバトンを渡したのかを詳しく見ていきましょう!
セイコーエプソン碓井氏の功績と次世代への引継ぎ
──“技術と共創”で築いた基盤を未来へと手渡す
退任する碓井稔氏は、セイコーエプソンの相談役としての顔とともに、2021年から長野県経営者協会の会長として県内経済を支えてきました。製造業出身ならではの現場感覚と、グローバル視点を併せ持つトップとして、さまざまな業界を横断するリーダーシップを発揮してきた人物です。
とくに評価されているのが、「産業の高度化」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進」に対する強いメッセージ。県内の中小企業に対しても、単なるIT導入ではなく、“本質的な業務改革”としてのデジタル化を根気強く訴え続けました。
また、セイコーエプソンの技術とネットワークを活かした教育連携も積極的に展開し、地元の学生たちに“モノづくりの本質”を伝える取り組みも多数実施。このように、経営者協会の会長としてだけでなく、地域社会と未来の人材育成への貢献が多方面から高く評価されています。
そのうえで、後任の松下氏へは「地元の企業、金融、行政をつなぐハブ役としての強化」という明確な課題と展望を手渡しているのです。つまり今回のバトンタッチは、単なる世代交代ではなく、役割とビジョンの“継承”でもあります。
このように、碓井氏の功績があったからこそ、松下新体制に対する期待感も高まっているわけです。
続いて、「松下新会長体制」でユーザーが期待している未来像について詳しく見ていきましょう!
地域経済はどう変わる?ユーザーが求める未来とその実現
──“持続可能な成長”に向けて、地元の企業と人材をどう動かすのか?
今回の会長交代は、長野県の経済界にとって「転換点」と言える出来事。多くのユーザーが期待しているのは、単なるトップの交代ではなく、協会全体がこれまで以上に開かれた組織となり、若い企業や新しい産業にも積極的に関わる未来です。
特に近年注目されているのが、「地域の稼ぐ力をどう高めるか?」というテーマ。人口減少や都市部への若者流出という課題のなか、地元で育ち、地元で働き、地元で活躍できるビジネスエコシステムの構築が求められています。
その中核に、これからの長野県経営者協会がどう関わるか。それが、次代の地元経済の命運を左右すると言っても過言ではありません。
この章では、ユーザーが心から求める「地域経済の未来像」――とくに若手起業家やスタートアップ支援、オープンな経営体制への変化などをテーマに掘り下げていきます。
若手経営者やスタートアップ支援の強化
──“支援のカタチ”が変わる!新体制に寄せられる現場からの期待
「もっと挑戦できる土壌が欲しい」「若手が活躍する場をつくってほしい」──そんな声が、長野県内の起業家や若手経営者から続々と上がっています。
松下新会長に対する期待の中心には、「スタートアップ支援の加速」があります。八十二銀行の頭取として、松下氏はすでにスタートアップ向け融資や成長支援ファンドの創設をリードしてきました。彼の指導のもと、創業初期の資金調達や経営ノウハウの提供がこれまで以上に手厚くなると見られています。
また、経営者協会としても、若手経営者を巻き込んだ勉強会やピッチイベントの開催が想定されており、「横のつながり」「縦の支援」両面からのサポート体制構築が進められています。
長野県という地域特性上、「首都圏に行かなければ成長できない」という固定観念が長らく根強くありました。しかし、今は地元でもDX、観光資源の再定義、農業スタートアップなど多様な分野でチャンスが広がっています。
こうした可能性を具現化するためにも、経営者協会の支援策が柔軟でスピーディであることが求められているのです。
では次に、松下体制が掲げる「経済団体の新たな方向性」について掘り下げていきましょう!
リーダー交代による経済団体の新たな方向性
──“開かれた組織”への進化で、変化に強い地域経済へ
松下正樹氏が新会長としてリードする長野県経営者協会には、これまでの「内向き」から「外向き」へのシフトが求められています。
具体的には、旧来型の“大手企業中心”のネットワークから脱却し、スタートアップ、中小企業、さらにはフリーランスやNPOとも連携を深めることで、より開かれたプラットフォームを築く方針が期待されています。
たとえば、これまで参加が難しかった若手経営者や女性起業家への門戸を広げ、協会の“多様性”を意識した運営が進むと見られています。これは単なる表層的な改革ではなく、地域社会の課題に真正面から向き合う姿勢の表れです。
また、松下氏のこれまでの姿勢からも「スピード感ある意思決定」が期待されており、従来のような“時間をかけた合意形成”よりも、現場に即したアクションを重視する方向にシフトしていく可能性があります。
このように、リーダー交代は経済団体のスタンスそのものを見直す大きなきっかけに。今後は「多様な声が反映される組織」としての役割が、より強調されていくでしょう。
続いては、読者が最も気になるテーマ、「変化の中で企業がどう対処すればいいのか?」について具体的な対策をお伝えしていきます!
不安を解消するには?変化の中で企業が取るべき対策
──「ついていけない…」とならないために、今すぐ動ける準備とは?
経済団体のトップ交代は、変化とチャンスの両面を持ち合わせています。しかしそれは同時に、企業側にとって「どう付き合っていけばいいのか分からない…」という不安を生む場面でもあります。
特に、経営者協会の方針が変わることで、これまで受けられていた支援や情報共有の形も見直されるかもしれません。そんな中、企業として「どう動けばいいのか?」を知っておくことが、今後の経営判断に直結します。
このセクションでは、変化の波に乗り遅れないための“情報の取り方”と、“組織との関係の築き方”について具体策をご紹介していきます。
経営者協会との関係性を再構築する方法
──“つながり方”を見直すことで、地域経済の中でのポジションが変わる!
「協会って、大企業の集まりでしょ?」――そう感じて、これまで距離を置いてきた中小企業や若手経営者も多いかもしれません。しかし、新体制を迎える今こそ、その考えをアップデートするチャンスです。
長野県経営者協会は、会員制の経済団体でありながらも、地元経済全体の底上げを目的とした活動が多く、実は中小企業にとってもメリットの多い組織です。特に、地域連携の取り組みや補助金に関する最新情報、自治体との橋渡しなど、単独で得にくい“外部との接点”を構築できるのが大きな魅力です。
松下新会長の体制下では、より“オープンな会員参加”が期待されており、会合や意見交換会なども柔軟な形式が増えてくるでしょう。こうした場をうまく活用することで、自社のニーズや課題を発信し、他の会員企業とのマッチングや連携にもつながります。
「まずは会員にならなきゃ無理?」という疑問に対しても、最近では非会員向けの公開セミナーや合同イベントも増加傾向にあり、第一歩を踏み出すハードルは下がっています。
つまり、協会との関係性を“情報源”として見るだけでなく、“地域戦略の一部”として活用する姿勢が、今後の企業成長に不可欠なのです。
続いて、「新体制に乗り遅れない情報収集術」について、実践的なテクニックをご紹介していきます!
新体制に乗り遅れない情報収集術
──“情報は力”!現場に活きるニュースをキャッチする習慣を持とう
経済団体の方針や支援制度の変化にいち早く対応するには、何よりも「鮮度の高い情報」を得ることが欠かせません。特に新体制では、運営方針や施策がこれまでとは異なるテンポで動く可能性が高く、情報感度の差が企業の動きに直結します。
まず第一に活用したいのが、長野県経営者協会の公式サイトとSNSアカウント。ここでは総会の開催情報、新規事業の公募、会員向けのレポートなど、実践的な内容が日々更新されています。とくにX(旧Twitter)やFacebookでは、速報性の高い情報やイベント告知が多く発信されています。
次に、地元紙の経済面や業界専門メディアも見逃せません。八十二銀行の動向や協会に関する人事情報は、全国紙よりも地方メディアの方が圧倒的に詳しく、地域の空気感も伝わってきます。
さらに最近では、協会が発行する情報誌やメールマガジンの登録も要チェック。これは非会員でも読める場合があり、支援情報や補助金の募集要項、新設された委員会の動向などが網羅されています。
そして何よりも重要なのが、“情報を集めるだけで終わらせない”こと。気になるニュースやイベント情報を見つけたら、すぐに社内で共有し、対応策を考える習慣をつけましょう。
「えっ、そんな話もう出てたの?」なんて後悔する前に、今日から“情報キャッチのルーチン”を始めてみてはいかがでしょうか?
新体制に乗り遅れない情報収集術
──“情報は力”!現場に活きるニュースをキャッチする習慣を持とう
経済団体の方針や支援制度の変化にいち早く対応するには、何よりも「鮮度の高い情報」を得ることが欠かせません。特に新体制では、運営方針や施策がこれまでとは異なるテンポで動く可能性が高く、情報感度の差が企業の動きに直結します。
まず第一に活用したいのが、長野県経営者協会の公式サイトとSNSアカウント。ここでは総会の開催情報、新規事業の公募、会員向けのレポートなど、実践的な内容が日々更新されています。とくにX(旧Twitter)やFacebookでは、速報性の高い情報やイベント告知が多く発信されています。
次に、地元紙の経済面や業界専門メディアも見逃せません。八十二銀行の動向や協会に関する人事情報は、全国紙よりも地方メディアの方が圧倒的に詳しく、地域の空気感も伝わってきます。
さらに最近では、協会が発行する情報誌やメールマガジンの登録も要チェック。これは非会員でも読める場合があり、支援情報や補助金の募集要項、新設された委員会の動向などが網羅されています。
そして何よりも重要なのが、“情報を集めるだけで終わらせない”こと。気になるニュースやイベント情報を見つけたら、すぐに社内で共有し、対応策を考える習慣をつけましょう。
「えっ、そんな話もう出てたの?」なんて後悔する前に、今日から“情報キャッチのルーチン”を始めてみてはいかがでしょうか?