仲間に背中を押されて始まった会社

実は、自分から「会社を立ち上げたい」と強く思っていたわけではありません。どちらかというと、周りの仲間たちが「堀本さんやってよ」と声をかけてくれて、それに応える形で会社を始めました。そうした経緯があったからこそ、振り返ると本当に多くの人に支えられ、助けられてきたんだなと実感しています。だからこそ、会社をつくるなら、そこで働く人たちが一人の人間として、人生の一部を楽しめるような場所にしたいという想いが芽生えました。そんな思いから「生き生きと働くとは何か」と調べていくうちに、イタリア語で「生き生きと」という意味を持つ「vivo(ヴィーヴォ)」という言葉に出会いました。これまでビジネスの基本は「ヒト・モノ・カネ・情報」とされてきましたが、最近はその考えが変わってきています。「ヒト」は単なる資源ではなく、働く人たち自身の幸せこそが目的なのではないかと。働く人たちが幸せでなければ、いくら会社が利益を上げても意味がない。そんな風に考えるようになりました。今では、働く人たちが生き生きと楽しそうにしている姿を見ることが、何よりの喜びです。
一つの失敗が思い出させてくれた、企業理念の原点

創業当時、当社と学校との連絡ミスにより、卒業アルバムに一人だけ載っていない生徒がいたことが、後から発覚しました。業界では通常、こうした場合はシールを送って貼ってもらうという対応が一般的です。ところがご本人のご家庭にお詫びに伺った際、お母様から「そんな対応が本当に御社のやろうとしていることなんですか」と言われ、その言葉にハッとさせられました。そこで「これは理念に立ち返らなければいけない」と強く思い、当時あった何十冊ものアルバムをすべて回収し、全家庭に新たなものを届けるという決断をしました。大きな出費にはなりましたが、自分たちが本当にやるべきことが何なのかが明確になり、理念が深く浸透するきっかけになりました。
豊かな自然と非日常の風景が松本の強み

長野県は自然が豊かで、都会の人たちにとってこの山に囲まれた環境は本当に羨ましがられます。当店には結婚式は挙げず、写真だけを残したいというカップルたちが訪れてくれます。今のシーズンだと上高地でウェディングドレスを着て撮影したり、乗鞍の山頂で撮影したりと、自然の中での撮影が中心です。冬になるとスキー場での撮影や、松本城の周辺にある縄手通りや中町通りなど、風情あるスポットでの撮影も人気です。基本的には、お客様が希望する場所を伺いながら話し合いを重ね、実現していくスタイルです。長野市は新幹線でアクセスしやすいですが、松本は「陸の孤島」とも言われ、少し来づらい場所です。ただ、そういった距離感が逆に非日常感を生み、これからは強みになるのではと感じています。自然に囲まれたこの特別な環境で仕事ができることに、日々魅力を感じています。
家系図からカンボジア支援まで、絆を紡ぐ想いがすべての事業の軸に

写真を撮る仕事以外にも、自分史や家系図の作成を行っています。家系図は戸籍を遡って先祖を調べていくのですが、その過程で「これだけ多くの先祖がいて、その一人でも欠けていたら今の自分はいなかった」と実感します。過去を辿ることで、今この瞬間に生かされていることに気づき、未来の自分の生き方を考えるきっかけにもなる。そういう学びになると思うので、小学生にも教えてあげたいし、子どもたちに関わる活動ができたらと考えています。最近では、女性が家のことを守りたい、知りたいと家系図に関心を持つことも増えてきました。
また、私にはカンボジアで支援活動をしていた兄がいましたが、現地で交通事故により亡くなり、それを機に私が団体を引き継ぎました。「アジア子供教育基金」という団体で、現在は代表を務めています。以前は学校建設や井戸づくりなど様々な活動をしていましたが、現在は事業を絞り、職業訓練校で30人ほどの女の子たちがミシンを使って洋裁を学ぶ支援を行っています。彼女たちが将来独立して生計を立てられるようサポートしています。また、里子支援も行っており、日本人の方に「親」となってもらい、高校卒業まで経済的援助をしつつ、文通を通じて関係を築いていくという橋渡しの活動もしています。
当社の特徴は、スタジオ撮影や学校アルバムといった一つの事業に特化するのではなく、いくつかの事業を同時に展開している点にあります。それぞれがうまくリンクし合えば、事業としての強みがより発揮できると思っています。今は何ができるかを模索しながら、学校とスタジオ、自分史や家系、ウェディングなどを連携させ、新たな価値を生み出したいと考えています。そして私たちの理念である「絆を紡ぐ」という想いのもと、写真や美容、衣装といった枠にとらわれず、その延長にあるビジネスにも挑戦していきたいと思っています。今はその実現に向けて、社内でアイデアを出し合いながら新しい可能性を探っているところです。
共感力と視点で切り取る、写真の本質

カメラを使う上で、露出や色彩、構図など様々な技術的要素がありますが、私が一番大切にしているのは「シャッター動機」です。なぜその瞬間にシャッターを切ったのか、その理由こそが写真に深みを与えると考えています。私たちは人物を撮ることが多いので、被写体が何を求めているのか、その人の「人となり」はどんなものかを観察する力、そして共感する力が欠かせません。カメラの操作技術はもちろん大切ですが、それ以上に必要なのはコミュニケーション能力や共感力だと思っています。写真を撮る人と撮られる人の間には、最初は目に見えない境界線がはっきりと引かれています。その線を少しずつ越えたり戻ったりしながら、相手の反応を見て心の距離を縮めていく。そんな過程の中で、自分の弱さや人間らしさをさらけ出すことで、相手も心を開いてくれることがあります。そして初めて、その人らしい表情に近づける瞬間が生まれるのです。ただ、笑顔がその人らしいとは限りません。本当にその人らしい表情とは何かを見極める力が必要だと感じています。
また、私は視点の違いにも注目しています。例えば、小学生や幼稚園の頃に見ていた世界は、今見ると「こんなに小さかったんだ」と思うことがありますよね。それは、子どもたちがローアングルで世界を見ているからです。視線の先に空が広がっていて、世界がとても大きく感じられる。一方で大人になると視点は高くなり、目線の先は地面になり、空間が狭く感じられる。子どもの記憶にはそのローアングルの風景が残っています。だからこそ、その目線で撮った写真は、その子にとっての記憶と深く結びつくと考えています。どうすれば写真がその人の記憶と重なるのか、日々研究しながらシャッターを切っています。
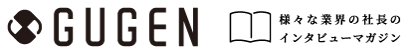
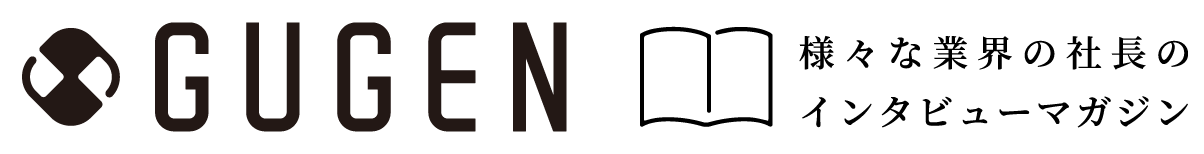


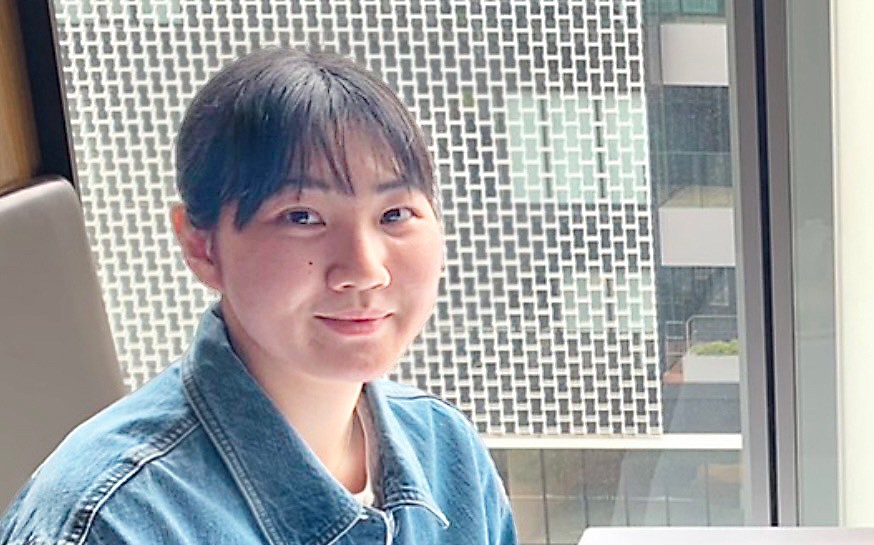
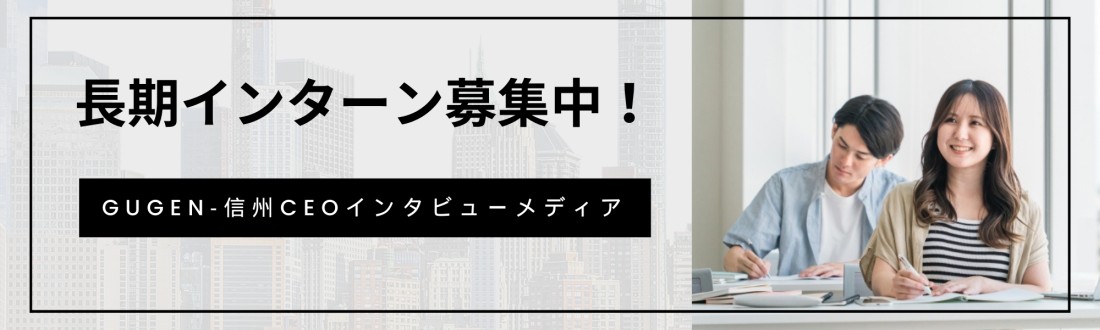

共感力と視点を大切に、シャッターを切る
「絆を紡ぐ」を理念とし、垣根を越えた挑戦を続ける